
「うちの子、散歩のたびに引っ張ってしまう…」と悩む飼い主さんは少なくありません。
犬が散歩で引っ張るのは、本能や不安が関係していることも。
この記事では、引っ張りの原因とやめさせ方をやさしく紹介。
繁殖引退犬にも安心して使える、穏やかなトレーニング法です。
この記事でわかること
犬は引っ張ってもいい?
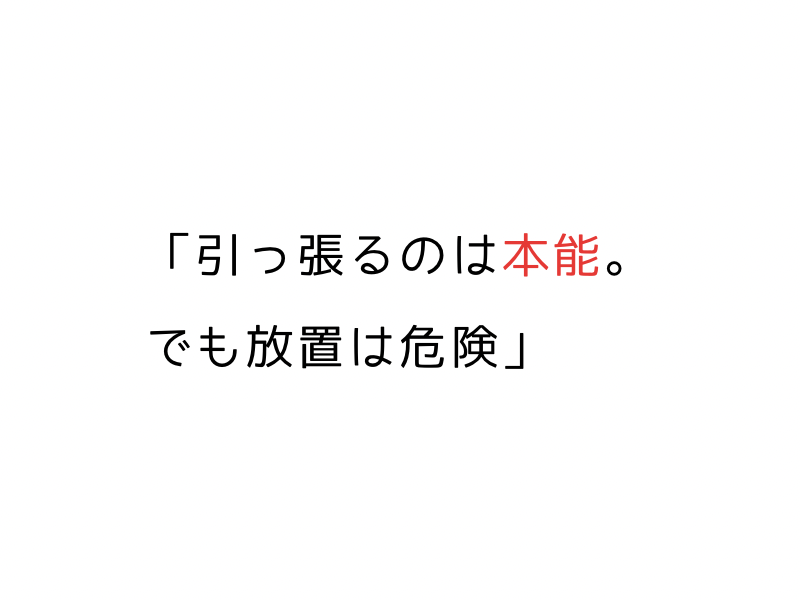
引っ張りは本能
犬は匂いや音にすぐ反応してしまう生き物。
散歩中に前へ前へと行きたがるのは、本能的に“世界を探検したい”気持ちの表れです。
放置のリスク
ただし強い引っ張りは、首や呼吸に負担をかけます。
飼い主が転倒したり、思わぬ事故につながるリスクもあるため。
「自然だから放っておく」で済ませるのは危険です。
横並びで安心
横に並んで歩けると
「飼い主と一緒なら安全」と犬は学びます。
これは安心感につながり、散歩そのものがより心地よい時間になっていきます。
引っ張る主な理由
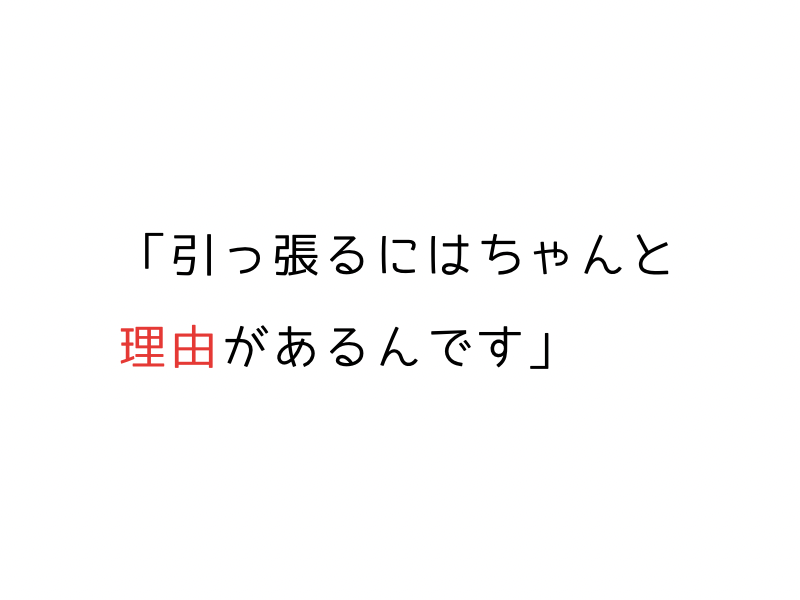
犬が引っ張る背景は一つではありません。
本能・癖・環境など、複数の原因が重なっていることが多いです。
外の刺激に夢中
散歩中は匂いや音、ほかの犬など新しい刺激がいっぱい。
犬はそれに反応してグングン前に進みたくなります。

笑ちゃんの場合、パートナーと行くと引っ張りますが、私とだと立ち止まることもあります。
前に出るクセ
リードが緩いまま前に出られると、犬は「前に行くと進める」と学習してしまいます。
習慣化すると、つい引っ張り続ける行動になります。
運動不足やストレス
十分に運動できていなかったり、家の中で刺激が少ない犬は、散歩中にエネルギーを発散しようと引っ張ることがあります。
リードが合図に
人がリードで引っ張ると犬は
「引っ張れば前に行ける」と勘違いすることも。
犬にとっては、リードの扱い方が行動の手がかりになっているのです。
興奮で走り出す
外の景色や匂いに夢中になると、犬は気持ちを抑えきれず前へ走ろうとします。
散歩が楽しくて仕方ないサインでもあります。
繁殖引退犬が引っ張る理由
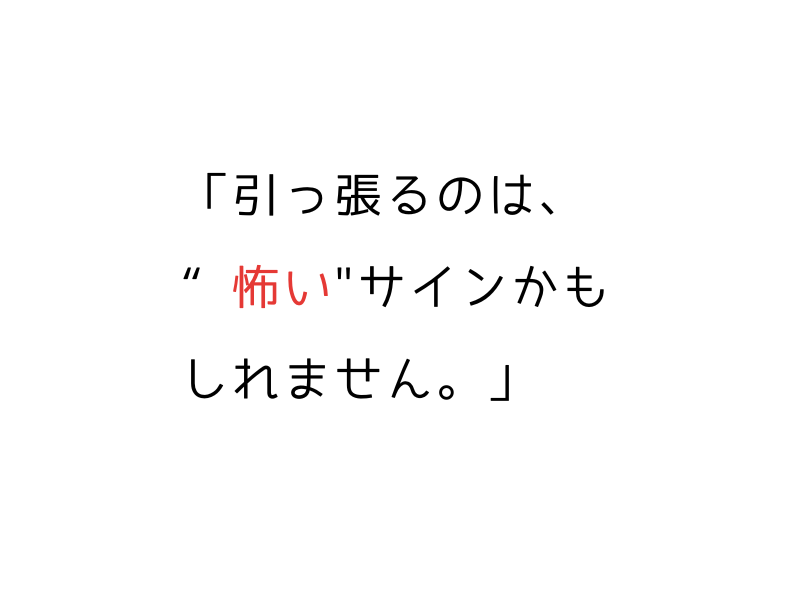
不安や緊張から早く歩こうとする
繁殖引退犬は、外の音や景色にまだ慣れていません。
怖い場所から離れたくて、ついリードを強く引いてしまうことがあります。
まずは静かな道で短く歩くことから。
「大丈夫だよ」と声をかけながら安心を積み重ねていくと、少しずつ落ち着いて歩けるようになります。
笑ちゃんの場合は犬を見かけたら、逃げるか、固まるかのどちらかです。
散歩コースを変える
いつも同じ道だと刺激が少なく、引っ張りぐせが抜けにくいことがあります。
安全な範囲でコースを少し変えると、犬の注意が分散し、落ち着いて歩けるようになります。
慣れた道と新しい道を組み合わせて、無理のないペースで変化をつけましょう。
実例:引っ張り癖の直し方
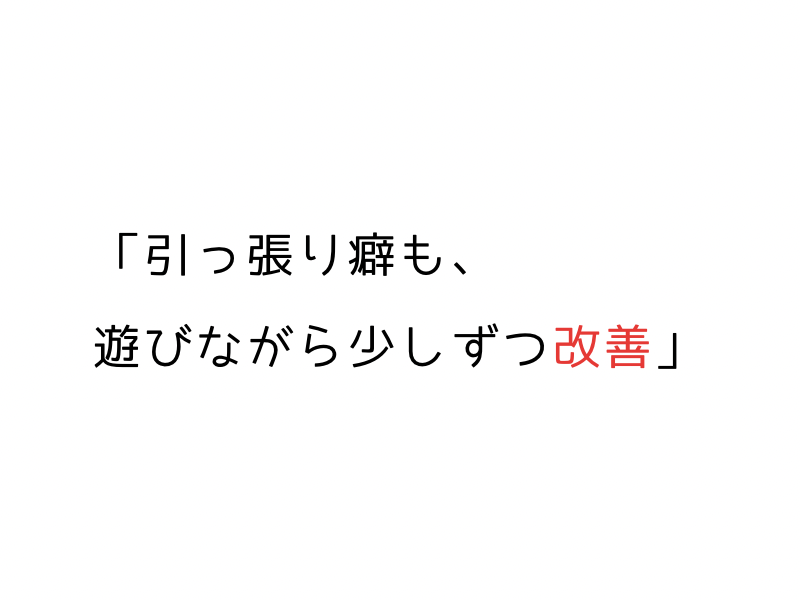
ブルドッグの実例
我が家の先住犬は散歩中にマーキングが大好きで、よく前に引っ張っていました。
そこで試したのがハズバンダリートレーニングです。
Uターン練習法
- STEP1犬が引っ張り始めたら
犬が引っ張った瞬間に、進行方向とは逆にUターンするか、その場で立ち止まります。
- STEP2犬が飼い主を見たら
犬がリードを緩めて飼い主に注意を向けたら、
前に進める/ご褒美を与えます。 - STEP3繰り返し実践
この繰り返しで、
犬は「引っ張るよりもリードを緩めた方が気持ちいい」と学習します。
報酬で横について歩く
Uターンは叱るためではなく、犬に正しい選択肢を示すサイン
「止まる→緩める→報酬」の流れを一貫させることで、徐々に引っ張り癖が改善されます
引っ張りをやめさせる方法
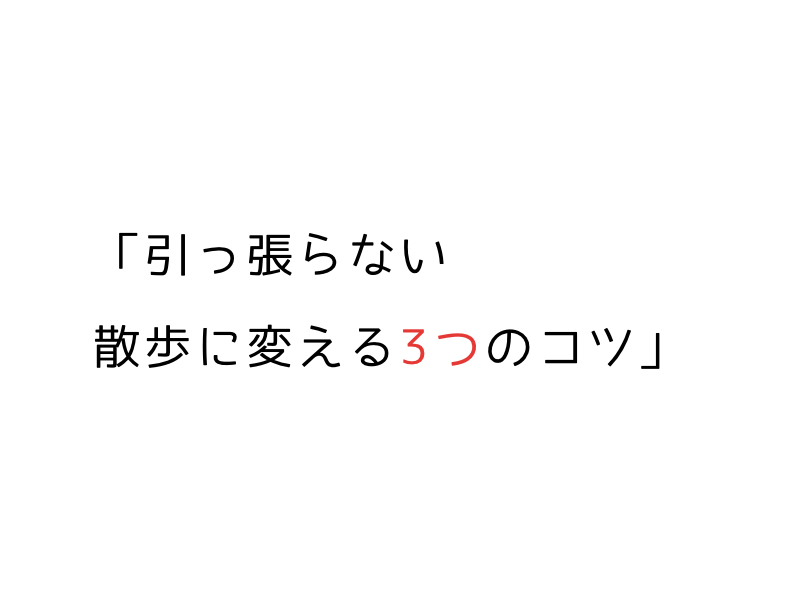
原因がわかると、対策も選びやすくなります。
ここでは、犬に負担をかけず改善できる方法を紹介します。
止まってリードを緩めよう
犬が引っ張ったら、その場で止まります。
リードが緩んだ瞬間に歩き出すことで、
「引っ張っても進めない」と学習します。
ごほうびで横歩き習慣
おやつや声かけで犬を横に誘導しながら歩きます。
楽しい体験と結びつけることで、自然と横について歩く習慣がつきます。
ハーネスを使おう
首に負担がかかる首輪より、胴に負担を分散できるハーネスが安全です。
リードと一緒に使うことで、引っ張り癖の練習もしやすくなります。
静かな場所で練習
最初は家の近くや人通りの少ない場所で練習すると、犬が落ち着いて学びやすくなります。
少しずつ環境を変えてステップアップしましょう。
縄張りを守ろうとしている
犬は散歩中、いつも歩く道や電柱などを「自分の縄張り」と感じています。
ほかの犬の匂いを見つけると、「ここは自分の場所だよ」と示したくなり、
ついリードを引っ張って先へ進もうとすることがあります。
うれしくて前に出ちゃう
散歩が大好きで、外に出ると気持ちが高ぶってしまう子もいます。
楽しい気持ちがあふれて、ついリードを引いて先に行こうとするのです。
歩き始めは少し立ち止まり、「ゆっくりね」と声をかけて落ち着かせましょう。
ペースを合わせるうちに、自然と落ち着いて歩けるようになります。
散歩コースを変える
いつも同じ道だと刺激が少なく、引っ張りぐせが抜けにくいことがあります。
安全な範囲でコースを少し変えると、犬の注意が分散し、落ち着いて歩けるようになります。
慣れた道と新しい道を組み合わせて、無理のないペースで変化をつけましょう。
ハズバンダリーをもっと知る
犬とのコミュニケーションや引っ張り癖改善の具体例は、田中雅絋氏の書籍でも詳しく解説されています。
実際の手順や応用例も豊富なので、「もう少し具体的に学びたい」という方はチェックしてみてください。
リードコントロールも選択練習
リードを使った操作も、犬に「どっちに動くか」を選ばせる練習です。
自分で選ぶことで、犬は納得して行動を変えやすくなります。
無理に引っ張り返さない
力で戻すのではなく、
犬が自分で「リードを緩めると進める」と気づくのがポイント。
叱らず、犬が自ら学ぶ環境を作ります。
まとめ|引っ張り癖改善のコツ
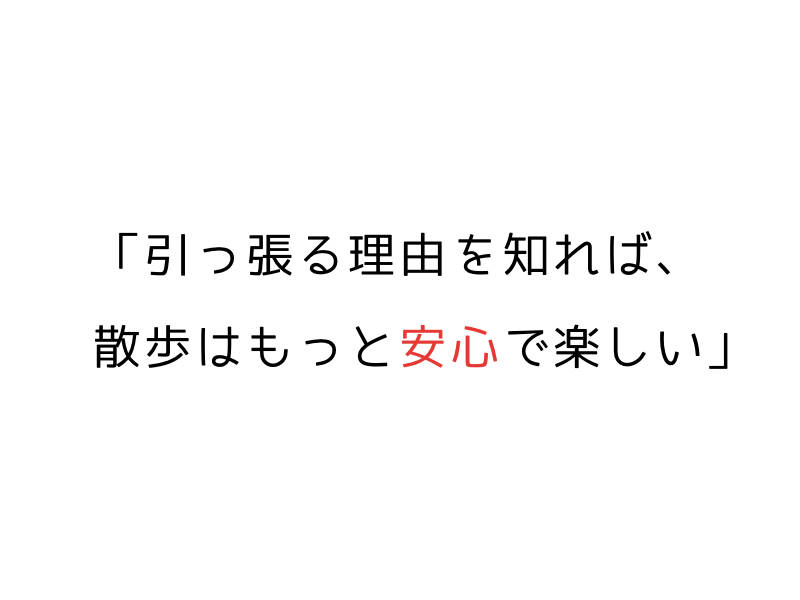
引っ張りは自然だけど危険
犬の引っ張りは本能によるものですが、放置すると首や体に負担がかかり、事故のリスクにもつながります。
原因を理解して改善できる
「止まる・ごほうび・環境づくり」の組み合わせで、引っ張り癖は徐々に改善可能です。
ハズバンダリートレーニングで安心散歩
犬が自分で選択して行動する環境を作ることで、散歩がより楽しく、安心な時間になります。
📖 全7回シリーズ|繁殖引退犬の迎え方
繁殖引退犬を迎えるまでのステップを、順を追って解説しています。
▶ STEP0:幸せのカタチ▶ STEP1:繁殖引退犬とは?
▶ STEP2:迎える前の判断材料
▶ STEP3:迎える準備と費用
▶ STEP4:犬舎見学チェックリスト
▶ STEP5:心の距離ゆっくり縮まる
▶ STEP6:迎えた後のやるべきこと
笑みと、ぼくが立ち止まったときに作った整理ページ
日々の中で気づいたことや、うまくいかなかったことを、
あとから見返せるように整理しています。
- 犬の散歩トラブルを全 部解決!歩かない・引っ張る・排泄・ストレス総まとめ
- 犬の下痢が教えてくれたこと|環境・季節・留守番を見直してわかったこと
- 犬のストレスを短く整理|よくある3つの場面と信頼関係で軽くする方法
- 犬の気持ちは行動に出ている|カーミングシグナルと行動心理をペットカメラで読み解く
※ 正解を押しつけるまとめではありません。
体験をもとに「整理」したページです。
注目記事

最後まで読んでくれてありがとう!
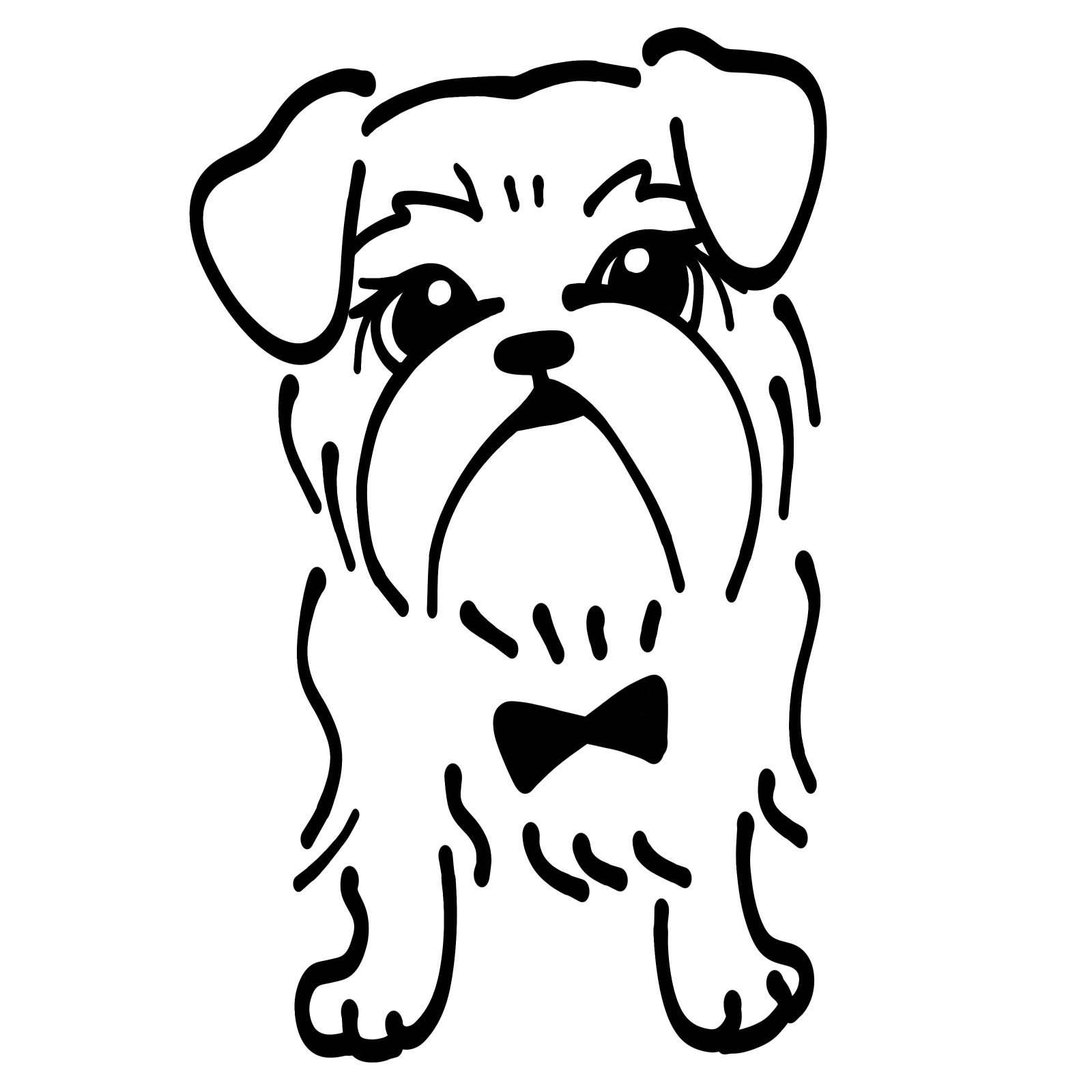
下のバナーを押してもらえると、更新の励みになります


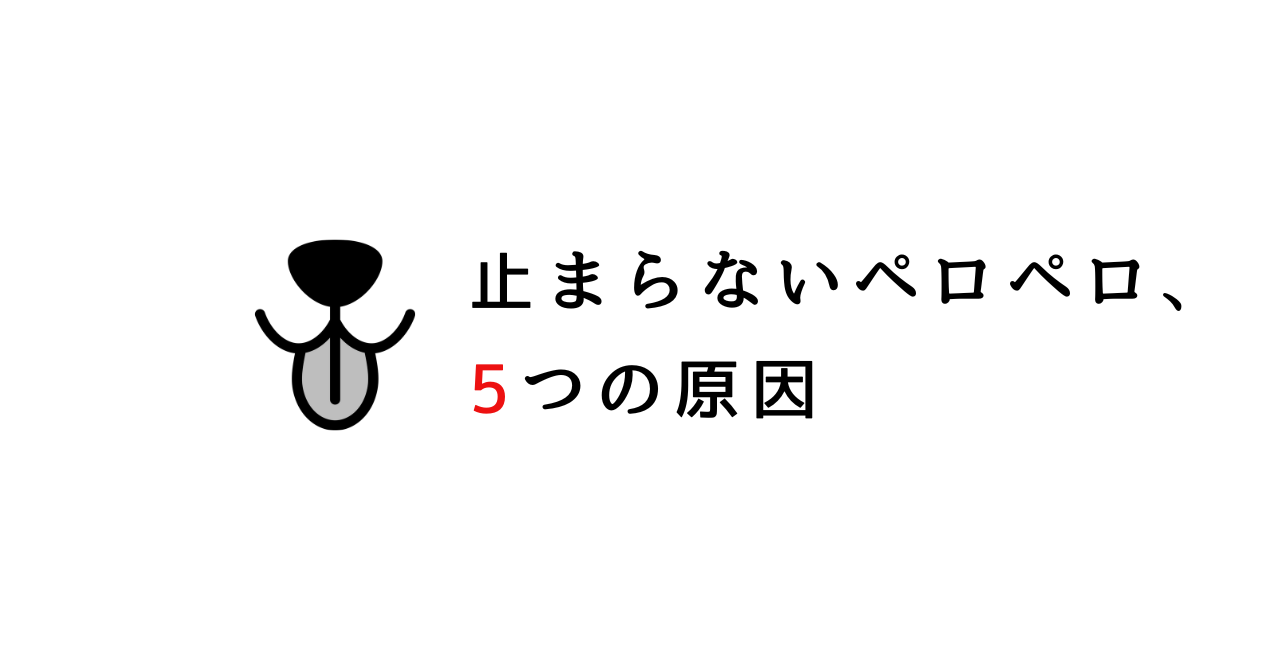
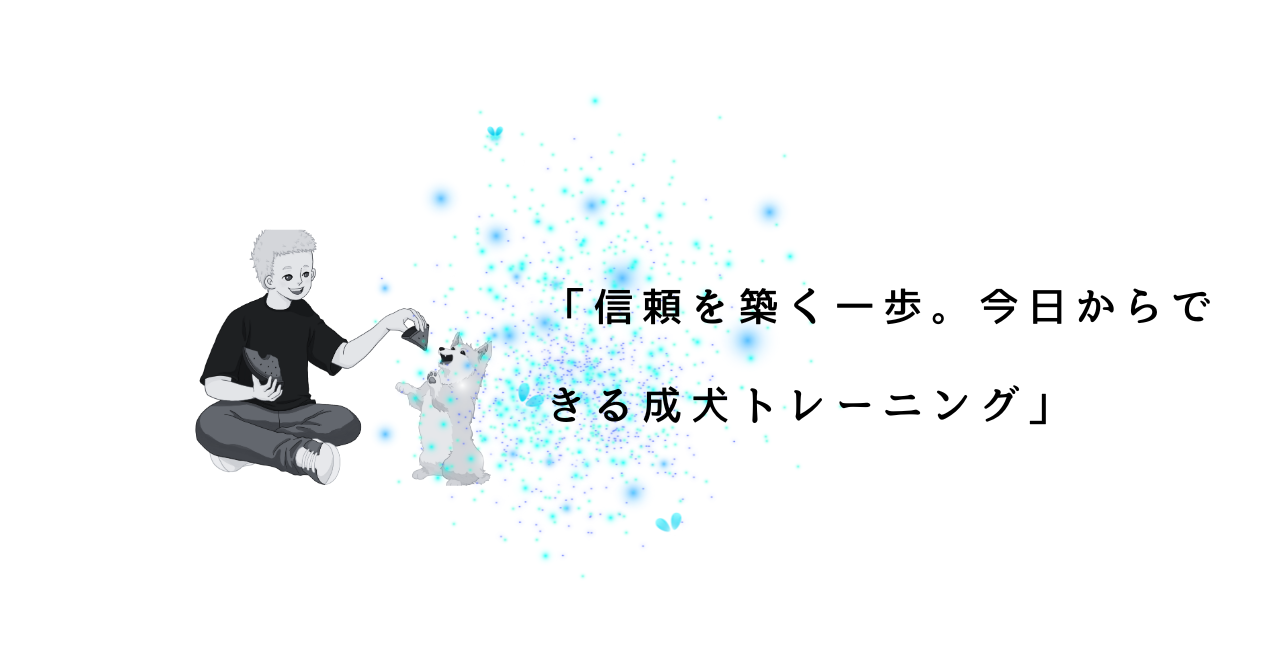
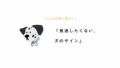

コメント